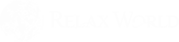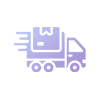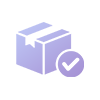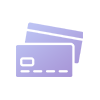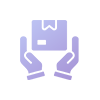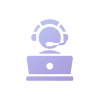長坂希望 (ながさか のぞみ) 先生 プロフィール

MT-BC(米国音楽療法士資格認定員会認定音楽療法士)
日本音楽療法学会認定音楽療法士
国立音楽大学声楽学科卒、
イリノイ州立大学大学院芸術学部音楽学科音楽療法・声楽専攻修了。
カリフォルニア州サンディエゴにて元全米音楽療法協会会長Dr.Barbara Reuer女史に師事し、ウェルネス、緩和ケアの音楽療法、ドラムサークル・ファシリテーションを経験する。
帰国後は、Here and Now、 喜怒哀楽や響き合う力を大切にした音楽でのよりよい生活づくりのお手伝いをしたいとRhythm in Lifeを立ち上げ、福祉、教育、医療現場や地域での臨床活動を行う。また、武蔵野大学、東京立正短期大学非常勤講師としての教育や、ドラムサークル・ファシリテーターとして、地域や企業、国際会議等で、より多くの方々に音楽の力を感じてもらおうと活動している。
著書に『音楽療法士』(新水社)、翻訳書に『ミュージック・セラピスト・ハンドブック』(株式会社ATN)『トゥギャザー・イン・リズム』(株式会社ATN)等がある
http://rhythm-in-life.com/
音楽療法とは何か? その魅力と効果に迫る
音楽は、リラックスしたり、気分を上げたり、私たちの感情に大きく影響を与えます。
では、その音楽を「療法」として活用するとはどういうことなのでしょうか?
今回は、音楽療法士として活躍する 長坂先生 に、音楽療法の基礎や実際の効果、日常生活での活かし方についてお話を伺いました。(後編)
音楽療法の実践 – 受動的 と 能動的
長坂先生:
音楽療法には 大きく2種類 あります。
● 受動的音楽療法 → 音楽を聴くことで心や身体に変化をもたらす
● 能動的音楽療法 → 一緒に演奏したり、歌ったり、身体を動かす
たとえば、リラクゼーションを目的に音楽を流して、脳波や血圧の変化を観察するのは 受動的音楽療法 です。一方、楽器を演奏したり、みんなで歌を歌ったりするのは 能動的音楽療法 ですね。

「音楽を聴くだけ」でも、やっぱり効果はあるんですね。
長坂先生:
はい、もちろんあります。ただし、 「ただ流しておけばいい」というわけではないんです。
同じ音楽を聴いていても、人によって受け取るものは違いますよね。だから、どんな音楽をどう聴くかが大切なんです。
音楽の「同質の原理」 – 疲れたときに適した音楽とは?
音楽を聴くとき、「リラックスしたいから癒やし系の音楽を聴こう」とか、「元気を出したいからアップテンポな曲をかけよう」と思うことがあるのですが、そういう選び方は正しいんでしょうか?
長坂先生:
はい、それが 「同質の原理」 という考え方です。
簡単に言うと、 「今の自分の気持ちや状態に合った音楽を選ぶことで、より効果的な影響を受けられる」 というものです。
たとえば…
● ものすごく疲れているとき → ゆったりした音楽を聴いて、心身を落ち着かせる
● 少し気分を上げたいとき → 軽快なリズムの音楽を聴いて、エネルギーを補充する
合わない音楽を選ぶと、かえってストレスになってしまう こともあります。
例えば、「疲れているときに、激しいロックを聴く」みたいな?
長坂先生:
そうですね。それだと、音の刺激が強すぎて逆に疲れてしまうこともあります。
だから、「今の自分に合った音楽を自然に選ぶこと」が大切なんです。実は、多くの人は無意識にこの原理を使っているんですよ。
音楽を意識的に聴くことの大切さ
普段から無意識に自分に合った音楽を選んでいるとしたら、それで音楽の効果を十分に得られていると考えて良いのでしょうか?
長坂先生:
確かに、私たちは普段から気分に合う音楽をなんとなく選んでいますよね。でも、 意識的に聴く ことで、より深い効果を得られるんです。
たとえば…
● テレビやスマホの音を一切消して、音楽だけを聴く
● 部屋の明かりを落として、リラックスした状態で音楽に集中する
● 深呼吸しながら、音楽のリズムに合わせて身体をゆっくり動かす

こうすると、ただBGMとして流しているときとは まったく違った効果 を得ることができます。
「ながら聴き」ではなく、音楽そのものに向き合う時間を作るということですね。
長坂先生:
そうです。意識的に音楽を聴くことで、自分の気持ちや身体の状態に気づきやすくなります。これは ストレスのセルフケア にもつながりますね。
音楽療法の実践例 – 認知症患者のエピソード
音楽療法が特に効果を発揮するのは、どのようなケースでしょうか?
長坂先生:
最近では、認知症の方への音楽療法 が注目されています。
「自分のことを忘れてしまったかもしれない」と家族に思われていた認知症の方が、音楽を聴いたことで普段見せない反応をしたり、「あの頃のお母さんに戻った」「お父さんに戻った」とご家族が感じることがあるんです。
たとえば、 昔よく歌っていた曲を聴くと、突然昔のように歌い出す ということがよくあります。また、興味深いのは、 身体が覚えている音楽は、認知症になっても忘れにくい ということ。
「ピアノを弾けた人が、認知症で話せなくなっても、ピアノの前に座ると指が自然に動くことがあるんです。」
こうした現象は、科学的にも研究が進められていて、音楽が脳に与える影響の大きさを示しています。

こういった現場に出会うと、音楽ってすごいなというよりも、人間てすごいな、と感じたりもしますね。
日常で音楽を活かすための具体的な方法
病気というほどでもないけど何か調子が悪いとか、音楽療法の現場になかなか参加できない場合などに、私たちが日常の中で手軽に音楽療法を取り入れるには、どうしたらいいでしょう?
長坂先生:
ポイントは 「意識的に音楽を使う」 ことですね。
たとえば…
1. 「今の気分に合った音楽を選ぶ」 → 明るい音楽!などにこだわらず自然と惹かれる曲を選ぶ
2. 「音楽に集中する時間を作る」 → スマホやテレビを消し、音楽だけをじっくり聴く
3. 「身体を動かしながら聴く」 → 深呼吸をしながら聴いたり、リズムに合わせて軽く身体を揺らす
このように、「ながら聴き」ではなく、 積極的に音楽と向き合うことが大切です。
ありがとうございます。ストレスケアや、気持ちの持ちようを変えることなどに活かしていきたいと思います。その先にある音楽療法のこともこれまでより少し身近に感じられました。
長坂先生:
そうなんです。「音楽療法」と聞くと難しく感じるかもしれませんが、 音楽を意識的に使うだけで、私たちの心と身体に大きな影響を与えますので、ぜひ取り入れてみてほしいですね。
ありがとうございました。
最後に長坂先生の現在の活動についても改めてご紹介いただけますか?
長坂先生:
私は3本柱でやりたいと思って続けていることがあって
● 音楽療法の臨床:現場に入って実践をすること
● 普及:音楽療法を知ってもらうことや、いまは教育畑で保育の学生さんたちに音楽療法を教えています
● 研究:論文書いたり、発表したり、活動をまとめること
といった3つの事を中心に活動しています。
この度は色々なお話を聞かせて頂きありがとうございました。
前編はこちら:音楽療法の可能性とは? 音楽療法士・長坂先生に聞く!
おすすめの音楽:長坂希望先生監修作品
ジャケットのクリックでの全曲ご試聴が可能です。
◆作品名
眠りのピアノ~ アヴェ・マリア ~
◆アーティスト
Classy Moon
◆商品説明
シューベルト、カッチーニ、グノーによる「3大アヴェ・マリア」の他、ショパン、ベートーヴェン、モーツァルト、ラヴェル、チャイコフスキーらの数々のピアノの名曲を収録した癒しのピアノ作品。
☆ブックレットに長坂希望による全曲解説掲載
◆トラックリスト
01. シューベルト:アヴェ・マリア(エレンの歌第3番)
02. ベートーヴェン:エリーゼのために
03. エルガー : 愛の挨拶
04. ショパン:ワルツ 作品64-2
05. ラヴェル : 亡き王女のためのパヴァーヌ
06. シューマン:メロディー(『子供のためのアルバム』より)
07. チャイコフスキー:フランスの古い歌(『子供のためのアルバム』より)
08. ドビュッシー:アラベスク 第1番(『2つのアラベスク』より)
09. バダジェフスカ:乙女の祈り
10. アルベニス:前奏曲(組曲『エスパーニャ』より)
11. カッチー二:アヴェ・マリア
12. シューマン:知らない国々(『子供の情景』より)
13. ビゼー : ハバネラ(『カルメン』より)
14. ストリーボッグ:すみれ
15. ショパン:ワルツ 作品69-2
16. チャイコフスキー:悲しい歌作品40-2
17. モーツァルト : きらきら星変奏曲
18. メンデルスゾーン:春の歌(『無言歌集』より)
19. ベートーヴェン:ピアノソナタ第8番『悲愴』第2楽章
20. グノー : アヴェ・マリア
インタビュー取材・文 : RELAX WORLD 編集部